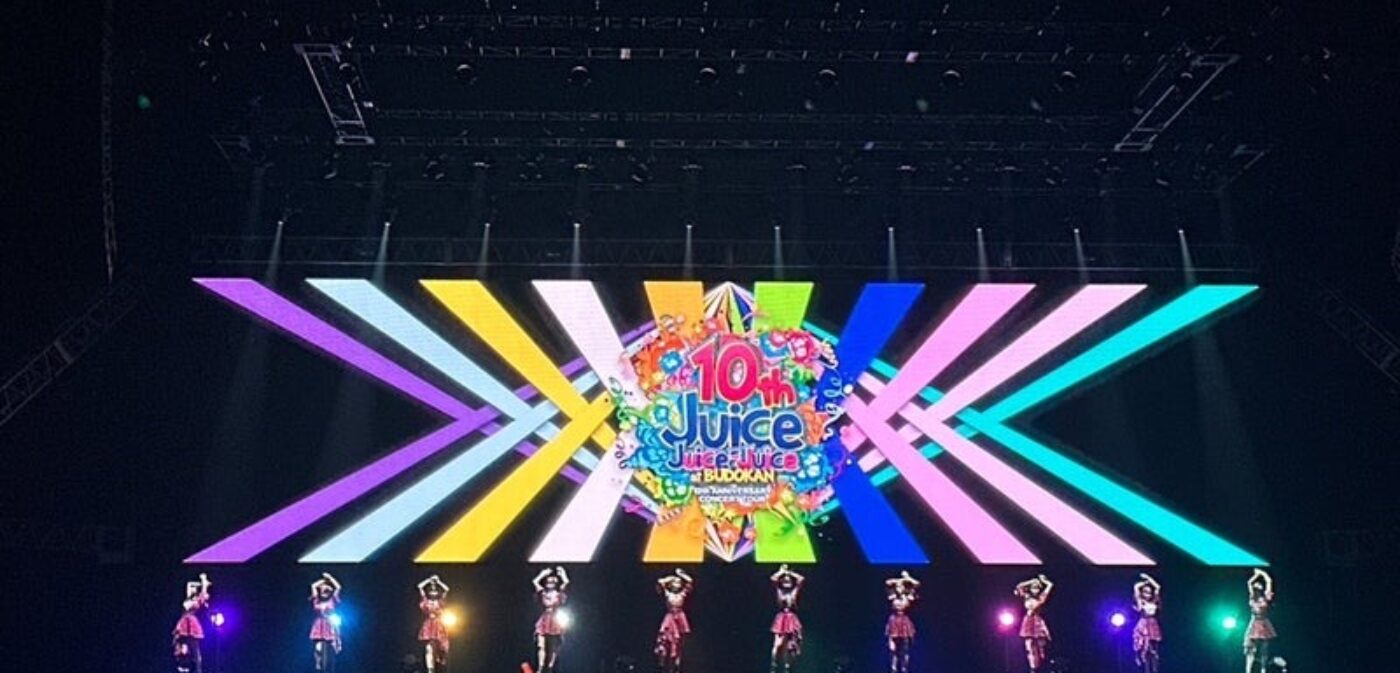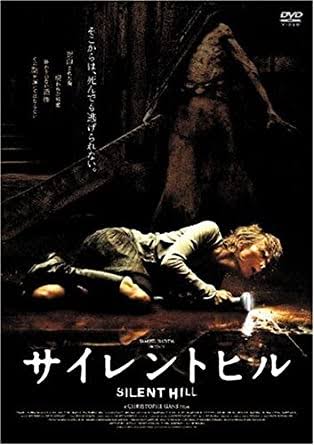ハサミはなぜ無くなるのか?
ハサミは使おうとするとき、定位置に無いことが多くあります。なぜでしょう?
散々探し回った後に思いもよらない場所から出てくることはありませんか?
特に職場や学校などでの「みんなでつかう」ハサミは要注意です。
ではなぜハサミはどこかへいってしまうのか考えてみました。
日常生活でハサミを使用した作業の特性を考察してみると
- 使った後の手作業が多い(整える、抑える、結ぶ、運ぶなど)
- ハサミを置いている定位置から離れて「作業する場所」に持っていく
- 専門的な従事者(理・美容師など)を除いて常に使うものでは無い
- カッターや包丁よりも構造的に安全性が高く「刃物」であることの意識がやや低い
などがあり、ハサミは「行動と行動の間に必要になっている」ことがわかります。つまり「なにかするための途中で入り込んでくる」作業です。
ハサミを使った作業は行いながらも、次の事や他の事を考えており「今現在」に意識がフォーカスされていないという認識に落ち着きました。
見つからないハサミは「誰がどこで何のために使ったか」を起点として記憶と場所を追跡してみましょう。作業中に手を使うために一時的に置いたことを忘れている場合がよくあるケースです。
刃物を使った先業中と作業後にも十分注意をはらって、元の場所に戻しましょう。